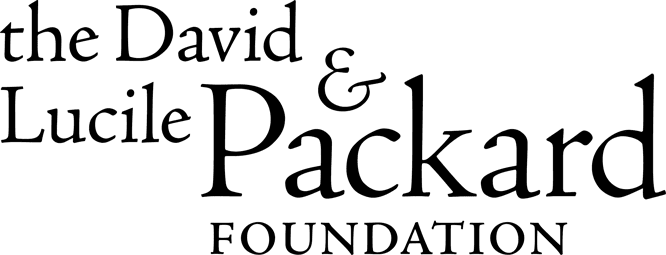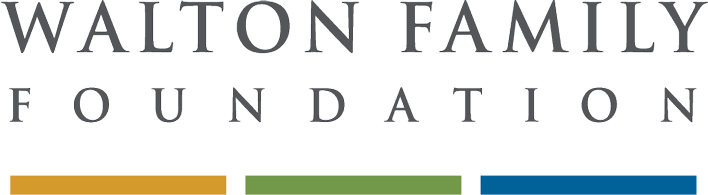JAPAN SUSTAINABLE SEAFOOD AWARD2025
FINALISTS
第6回ジャパン・サステナブルシーフード・アワード ファイナリスト発表
 リーダーシップ部門・ファイナリスト紹介
リーダーシップ部門・ファイナリスト紹介
単独、もしくは複数の企業、組織、個人による、画期的な取り組みで業界のパイオニア的存在となったプロジェクトを表彰します。周囲が次に続くような取り組みであることを重視します。

シェフチームによる水産資源と食文化を未来につなぐプロジェクト「Chefs for the Blue」
一般社団法人Chefs for the Blue
【ファイナリスト選定理由】
長年に渡り、飲食業界を巻き込み、行政との対話、教育など多角的に活動が広がっている点が評価されました。シェフが水産資源の危機を自ら発信し、生産者・流通・消費者をつなぐ取り組みは、このプロジェクトならではの強みです。また、若者たちへ活動の対象を広げようとしていることを高く評価します。これからこうした活動をサステナビリティへの具体的成果に繋げていくことが今後の課題であり、具体的ゴールの設定や成果のデータ化などアピールの仕方の改善を期待したいと思います。
一般社団法人Chefs for the Blueは、2017年に日本の水産資源の危機に危機感を抱いたフードジャーナリストの呼びかけで、東京のトップシェフたちが集まった勉強会から始まりました。
2021年には京都チームが発足し、2025年からは飲食業界全体へと学びを広げるオンラインコミュニティ、「THE BLUE COMMUNITY/ブルーコミュニティ」を展開。政策提言をはじめとした行政との対話を実施してきたほか、一般市民向けの、メンバーシェフによる多彩なシーフードイベント、次世代を担う学生向け教育プログラム(サステナアワード2024「農林水産大臣賞」受賞)など、多角的な活動を展開しています。
2023年にはアンケート調査によって、飲食店のオーナーや調達担当者約1,300名から記名回答を集め、業界の声を行政に届けました。こうした取り組みを通じて、シェフが生産者・流通・生活者をつなぐ存在として、持続可能な水産資源利用の未来を描いています。
関連リンク

養魚飼料を通じて日本の養殖業を持続可能に導く
~日本初のASC Feed基準取得プロジェクト~
スクレッティング株式会社
【ファイナリスト選定理由】
日本で初めてASC飼料基準認証を取得し、国産養殖飼料の持続可能性を切り拓いた点が評価されました。資源枯渇やIUU漁業、労働環境といった課題に正面から向き合い、国際基準を国内に導入したことは画期的です。今後は、業界全体への波及、持続可能性とビジネスの両立をどのように広げていくかが注目されます。
スクレッティング株式会社は、生産者やサプライヤーと連携し、2025年2月に日本で初めてASC飼料基準認証を取得しました。養殖業で使用されている飼料の中には、持続可能でない漁業・農業に由来する原料に依存しているものもあり、養殖用飼料は資源枯渇やIUU(違法・無報告・無規制)漁業、労働環境などの課題と結びついています。
本プロジェクトは、持続可能な原料調達を推進し、養殖業と漁業・農業の負の連鎖を断ち切ることを目指しました。原料サプライヤーとの対話や購買活動を通じて、ASC飼料基準が求める環境・労働条件の担保に取り組み、世界水準の持続可能性を飼料に反映しました。日本国内での認証取得は難しいとされてきましたが、今回の達成により、持続可能性とビジネスの両立が可能であることを証明することができました。今後も飼料供給と支援を通じて、ASC認証の普及と日本の養殖業の持続的発展に貢献していきます。
関連リンク
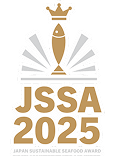

循環型藻場造成「積丹方式」によるウニ増殖サイクルとブルーカーボン創出プロジェクト
北海道積丹町におけるブルーカーボン創出プロジェクト協議会
【チャンピオン選定理由】
磯焼けによって失われた藻場を再生し、ウニ資源を循環的に活用する「積丹方式」が機能し、大きな成果を上げていることが高く評価されました。廃殻肥料化による藻場造成や収益向上、CO₂削減を同時に実現した点がポイントであり、ウニを資源に持つ他地域にも応用可能な地域モデルとして、さらなる展開が望まれます。
積丹町では、かつて磯焼けによるコンブの減少によってウニ生産量が落ち込み、観光や漁業に大きな影響が出ていました。本プロジェクトは、2009年に漁業者が中心となって「海の森づくり」を開始し、ホソメコンブ藻場の再生に成功。さらに2019年には、廃棄物だったウニ殻を肥料化して藻場造成に活用する独自手法「積丹方式」を開発しました。
その結果、2023年には約1.5ヘクタールのコンブ場を再生し、ウニ剥き身重量で444キログラム、約3,550万円の増収を実現。加えて、Jブルークレジットにより6.4トンのCO₂削減量を認証され、その売却益を次の活動に活用する循環も確立しました。廃棄物削減と資源回復、経済効果を同時に達成する世界初の試みとして注目されています。
現在は「海業」の核事業として官民連携の協議会が立ち上がり、2025年以降は藻場造成や肥料製造の拡大、エコツーリズムとの連携を通じて、地域創生と気候変動対策を一体で推進しています。
関連リンク
 コラボレーション部門・ファイナリスト紹介
コラボレーション部門・ファイナリスト紹介
複数の企業、組織、もしくは個人がノウハウを共有することで実現したプロジェクト(同業者間の協働も含む)を表彰します。複数組織が協働することで業界により大きな影響を与える取り組みであることを重視します。

佐渡島発-海藻の新たな可能性を探究するプロジェクト
佐渡島自然共生ラボ
【ファイナリスト選定理由】
漁業者や研究者、行政、高校生までが連携し、海藻を軸に里海の再生と文化の再興に挑んでいる点が評価されました。能登の海女たちとの交流を含む活動は、教育的な広がりも持ち、地域資源の新たな可能性を示しています。今後は、こうした知見をさらに発信し、海藻を核とした地域活性化モデルへ発展していくことが期待されます。
佐渡島自然共生ラボの海藻プロジェクトでは、漁業者、行政、研究者、高校生、飲食店らが参画し、海藻を活かした里海再生と海藻文化の再興に取り組んでいます。
佐渡では食材や肥料、建材、祭礼、遊具など多様な使途に海藻が活用されてきましたが、環境変化や担い手減少、消費者の海藻離れなどにより文化の衰退が進んでいます。ワカメ養殖従事者は114名(2013年)から48名(2023年)に減少しており、2030年までに、この担い手減少の緩和や3件の養殖事業の新規展開実現を目指します。ワカメ、コンブ、ナガモに加え、ウミゾウメン、ツルモ、クロモなど未利用海藻の利活用にも挑戦。能登半島地震後には輪島の海女たちも参加し、佐渡と能登が交流を深めながら里海保全と海藻文化の再興に取り組んできました。
こうした学びを共有し、保全・生産・消費の各現場をつなぐことで、海藻フードビジネスコミュニティを強化し、地域の暮らしの豊かさと健全な里海の実現を目指しています。
関連リンク
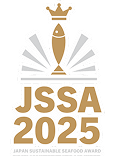

現場起点で日本の海の未来を考える『水産未来サミット』
水産未来サミット実行委員会
【チャンピオン選定理由】
全国の漁業者や行政、研究者など多様な立場の関係者が集い、本音の議論から実際のプロジェクトや政策提言につなげている点が高く評価されました。従来にない全国規模の共創の場を自立的に築き、現場から水産改革を動かす仕組みは先進的で、他の地域や分野への波及も期待されます。今後は成果の可視化や長期的な方向性の提示が重要な鍵となり、持続的な成長に注目が集まります。
水産未来サミットは、日本の海の未来を現場から変革するため、全国の漁業者や水産会社をはじめ、行政、研究者、企業、NGOなど多様な立場の人々が集い、とことん議論する合宿形式の共創型サミットです。資源枯渇やIUU漁業、海洋環境の悪化といった大きな課題に対し、地域や漁法を超えて知識や経験を共有し、議論だけでなく具体的なアクションにつなげている点が特徴です。
2024年に宮城県気仙沼で開催された第1回には約120名、2025年に鹿児島県垂水市で開催された第2回には約200名が参加。第1回には15件、第2回には22件のプロジェクトがそれぞれ立ち上がり、提言書は国の政策議論の場にも届けられ、資源管理や調査予算の拡充などにつながりました。
自己資金で運営する独立性と、女性漁師や経営者、社会課題解決の専門企業など、多様な参加者との本音の議論から生まれる数多くの協働プロジェクトを創出しています。2026年3月には能登での第3回サミット開催を予定し、2030年までに現場起点の水産改革を実現することを目指しています。
関連リンク


インドネシア・エビ養殖業改善プロジェクト(AIP) 第三期
日本生活協同組合連合会
【特別賞選定理由】
インドネシアでのASC認証取得やマングローブ再生活動など、国際協働による持続可能な養殖モデルを構築してきた点が評価されました。ブラックタイガー養殖という困難な分野で改善を積み重ね、生態系保全と地域の暮らしを両立させてきたことは、アジア地域における先駆的な成果です。長年の取り組みをさらに発展させ、他魚種や国内への知見還元につなげていくことが期待されます。
日本生活協同組合連合会は、現地エビ加工会社や世界自然保護基金(WWF)ジャパン・同インドネシアと協力し、環境や社会に配慮した持続可能なブラックタイガーエビ養殖をめざす取り組みを進めています。本プロジェクトは2017年7月に開始され、第三期が進行中です。南スラウェシ州や中部ジャワ州でASC認証に基づく養殖業の改善に取り組み、2024年3月に中部ジャワ州の養殖池がASC認証を取得、同年10月からラベル付き商品の販売を開始しました。認証を受けた養殖池の面積は現在11.1ヘクタール・生産者数4名ですが、2026年6月までに100ヘクタール・30名以上を目標としています。認証取得に向けては、ASC基準である、養殖池での稚エビ池入れから収穫までの生残率25%以上の達成が大きな課題となりました。プロジェクトの活動を通じ、当初の7〜13%から、現在は24〜27%に改善しました。
アチェ州では親エビ漁業改善のサポートを通じ、漁業管理計画が策定され州知事令として承認。また、主要漁村の漁業者の約3割がライセンスを取得しました。
マングローブの再生活動は、現在までに25.4ヘクタールで再生を行い、このうち16.2ヘクタールで根付きが確認されています。これらの活動を通じ、生態系保全と地域住民の暮らしの向上を両立させ、持続可能な水産業モデルの確立を目指しています。
関連リンク

指宿市 "山川の海のゆりかご" ブルーカーボンプロジェクト
⼭川町漁業協同組合
【ファイナリスト選定理由】
漁協を中心に地元企業や学校、行政が協力し、ブルーカーボン創出に挑戦している点が評価されました。アマモを食害する魚を活用した弁当開発など、ユニークな工夫も注目され、地域の関心を高めています。始動段階にある取り組みの収益化など、外部からのサポートも確保しながら、プロジェクトの持続的な成長へと導くことが今後の課題となります。
鹿児島県指宿市山川の沿岸域は、日本のアマモ場の南限です。本プロジェクトでは、山川町漁業協同組合を中心に、県内の様々な企業等が連携してこのアマモ場の再生と保全を目指しています。アマモ場は稚魚の育成の場として「海のゆりかご」と呼ばれ、水産資源の回復に加え、光合成で取り込んだCO₂を長期的に炭素として海底や深海に蓄積する「ブルーカーボン」の働きを持ち、気候変動対策にも貢献します。しかし近年、環境変化や魚類の食害により「磯焼け」と呼ばれる藻場の消失が進み、大きな課題となっています。こうした中、同漁協は地元企業や学校と連携し、約20万粒のアマモ種を採取、49本(約245㎡)のアマモマットを設置しました。
また、環境教育や体験型観光も展開し、藻場の重要性を地域に広めています。さらに環境省「自然共生サイト」の認定や県内初のJブルーカーボンクレジット(0.4トン分)の取得も達成。食害魚を活用した弁当の開発など新たな価値創出にも挑戦しており、新たな地域連携による持続可能なモデルとなることが期待されています。
関連リンク