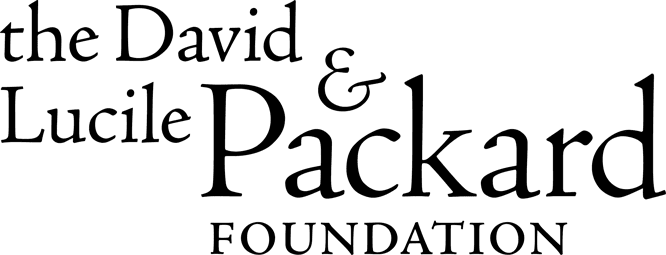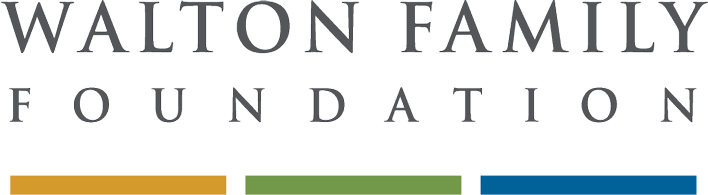- TOP
- プログラム
プログラム
【特別対談】TSSS2025の先に描く未来 〜私達がTSSSの開催を続ける理由〜
登壇者
-
花岡 和佳男
株式会社シーフードレガシー
創立者 / 代表取締役社長株式会社シーフードレガシー
創立者 / 代表取締役社長花岡 和佳男
フロリダの大学にて海洋環境学および海洋生物学を専攻。卒業後、モルディブおよびマレーシアにて海洋環境保全事業に従事。2007年より国際環境NGOの日本支部でサステナブルシーフード・プロジェクトを企画・牽引。
独立後、2015年に東京でシーフードレガシーを創立し、CEOに就任。「海の自然・社会・経済のつながりを象徴する水産物(シーフード)を豊かな状態で未来世代に継ぐ(レガシー)」ことをパーパスに、境持続性および社会的責任が追求された水産物をアジア圏における水産流通の主流にすべく、システムチェンジを牽引。
2019年には SeaWeb Seafood Champion Award リーダーシップ部門でチャンピオンを受賞。先見性のあるビジョンと、国内外の水産業界、金融機関、政府、NGO、アカデミア、メディアなど、多様なステークホルダーをつなぐ、その卓越したリーダーシップにより、アジアの水産業界における革新的なリーダーとして注目されている。
・IUUフォーラムジャパン メンバー(2017年〜現在)
・G1海洋環境研究会アドバイザリーボードメンバー(2018年〜現在)
・世界経済フォーラム フレンズ・オブ・オーシャン・アクション メンバー(2021年〜現在)
・コアリション・フォー・フィッシャリー・トランスパレンシー 理事(2022年〜現在)
・コンサベーション・アライアンス・フォー・シーフード・ソリューション 理事(2023年〜現在)
・NIKKEIブルーオーシャン・フォーラム有識者委員および水産資源分科会座長(2023年〜現在)
・水産庁 太平洋広域漁業調整委員会 委員(2018年〜現在)
・水産庁 水産流通適正化推進会議 委員(2024年)
他
-
浅見 直樹
日経BP
専務取締役日経BP
専務取締役浅見 直樹
1985年、東京大学工学部卒業、1987年、東京大学大学院工学系研究科修士課程修了。第二次AIブームを受けて、機械設計における人工知能の応用を研究テーマに選ぶ。1987年、日経BP(当時の社名は日経マグロウヒル)に入社、日経エレクトロニクス編集部にて、コンピュータ・半導体分野を担当。1994年からシリコンバレーに駐在し、インテル、マイクロソフトなどIT業界を取材した。日経エレクトロニクス編集長、日経ビジネス発行人を経て、2013年に取締役、2019年に常務取締役、2023年に専務取締役。現在に至る。
好きな肴は、「鮎」と「鰺」。大阪・関西万博にてブルー・オーシャン・ドームを訪問し、海の大事さを学んできた。登壇プログラム
- 資料ダウンロード
登壇者
-
藤田 仁司
水産庁
長官水産庁
長官藤田 仁司
昭和62年(1987年)に農林水産省に入省し、水産庁資源管理部管理課長、水産庁漁政部企画課長、水産庁増殖推進部栽培養殖課長、水産庁資源管理部長、水産庁次長を歴任し、令和7年7月より現職に就く。
登壇プログラム -
ニーアル・オディー博士
カナダ漁業海洋省
戦略政策担当
上級次官補カナダ漁業海洋省
戦略政策担当
上級次官補ニーアル・オディー博士
2021年4月に現職に就任する以前、オディー博士は2018年3月より、カナダ環境気候変動省の傘下にあるカナディアン・ワイルドライフ・サービスの次官補・副次官補を務めた。それ以前には、2011年より、カナダ天然資源省で気候変動影響・適応担当課長、副大臣付シニア・アドバイザー、電力資源局長などさまざまな職務を歴任している。
オディー博士は2006年に公務員としてのキャリアをスタート。まずはカナダ環境省で産業界の温室効果ガス排出削減のための政策・法律・規制の提案に携わった。そしてその後、枢密院事務局にて、漁業海洋大臣・天然資源大臣・環境大臣が担当する提案や政策課題について、首相・内閣・枢密院事務官に助言を与えてきた。
オディー博士はニューファウンドランドメモリアル大学で生物と哲学の学士号を、そしてオックスフォード大学で、ローズ奨学生として修士号と博士号を取得している。登壇プログラム -
更家 悠介
サラヤ株式会社
代表取締役社長 兼 2025年大阪・関西万博 パビリオン ブルーオーシャン・ドーム名誉館長サラヤ株式会社
代表取締役社長 兼 2025年大阪・関西万博 パビリオン ブルーオーシャン・ドーム名誉館長更家 悠介
1951年生まれ。74年大阪大学工学部卒業。75年カリフォルニア大学バークレー校工学部衛生工学科修士課程修了。76年 サラヤ株式会社入社。98年代表取締役社長に就任、現在に至る。日本青年会議所会頭、(財)地球市民財団理事長などを歴任。(特活)ゼリ・ジャパン理事長、大阪商工会議所常議員、ボルネオ保全トラスト理事、などを務める。モットーは、あらゆる差別や偏見を超えて、環境や生物多様性など地球的価値を共有できる「地球市民の時代」。主な著書に『地球市民宣言 ビジネスで世界を変える』(日経BP社)などがある
登壇プログラム
- 資料ダウンロード
【特別トークセッション】日経ブルーオーシャンが提言する日本主導のブルーエコノミーモデル
登壇者
-
角南 篤
公益財団法人笹川平和財団
理事長公益財団法人笹川平和財団
理事長角南 篤
公益財団法人笹川平和財団理事長、昭和音楽大学学長、デロイトトーマツ戦略研究所代表理事、政策研究大学院大学学長特命補佐・客員教授、早稲田大学ナノ・ライフ創新研究機構客員教授。専門は国際関係論、公共政策論(科学技術・イノベーション政策)。
内閣府参与を経て、内閣府沖縄振興審議会会長、文部科学省日本ユネスコ国内委員会副会長、内閣官房経済安全保障法制に関する有識者会議委員、内閣府総合科学技術・イノベーション会議専門調査会委員等を務める。その他、国連海洋科学の10年国内委員会共同座長、NIKKEIブルーオーシャン・フォーラム有識者委員会共同座長、JAXA宇宙戦略基金プログラムオフィサー、JAXA衛星地球観測コンソーシアム会長、月面産業ビジョン協議会共同座長等を務める。
コロンビア大学政治学博士(Ph.D.)、コロンビア大学国際関係・行政大学院国際関係学修士(MIA)、ジョージタウン大学外交学学士(BSFS)。 -
藤田 香
東北大学グリーン未来創造機構・大学院生命科学研究科教授、兼、日経ESGシニアエディター
東北大学グリーン未来創造機構・大学院生命科学研究科教授、兼、日経ESGシニアエディター
藤田 香
富山県魚津市生まれ。東京大学理学部物理学科卒。日経BPに入社し、日経エレクトロニクス記者、ナショナルジオグラフィック日本版副編集長、日経エコロジー編集委員、日経ESG経営フォーラムプロデューサー、日経ESGシニアエディターなどを歴任。生物多様性や自然資本、持続可能な調達、ビジネスと人権、ESG投資、地方創生などを専門とする。東北大学教授として「ネイチャーポジティブ発展社会実現拠点」の副拠点長を務める。環境省中央環境審議会委員。地球環境戦略研究機関(IGES)理事。NIKKEIブルーオーシャン有識者委員会共同座長。近著に『ESGとTNFD時代のイチから分かる生物多様性・ネイチャーポジティブ経営』などがある。
-
花岡 和佳男
株式会社シーフードレガシー
創立者 / 代表取締役社長株式会社シーフードレガシー
創立者 / 代表取締役社長花岡 和佳男
フロリダの大学にて海洋環境学および海洋生物学を専攻。卒業後、モルディブおよびマレーシアにて海洋環境保全事業に従事。2007年より国際環境NGOの日本支部でサステナブルシーフード・プロジェクトを企画・牽引。
独立後、2015年に東京でシーフードレガシーを創立し、CEOに就任。「海の自然・社会・経済のつながりを象徴する水産物(シーフード)を豊かな状態で未来世代に継ぐ(レガシー)」ことをパーパスに、境持続性および社会的責任が追求された水産物をアジア圏における水産流通の主流にすべく、システムチェンジを牽引。
2019年には SeaWeb Seafood Champion Award リーダーシップ部門でチャンピオンを受賞。先見性のあるビジョンと、国内外の水産業界、金融機関、政府、NGO、アカデミア、メディアなど、多様なステークホルダーをつなぐ、その卓越したリーダーシップにより、アジアの水産業界における革新的なリーダーとして注目されている。
・IUUフォーラムジャパン メンバー(2017年〜現在)
・G1海洋環境研究会アドバイザリーボードメンバー(2018年〜現在)
・世界経済フォーラム フレンズ・オブ・オーシャン・アクション メンバー(2021年〜現在)
・コアリション・フォー・フィッシャリー・トランスパレンシー 理事(2022年〜現在)
・コンサベーション・アライアンス・フォー・シーフード・ソリューション 理事(2023年〜現在)
・NIKKEIブルーオーシャン・フォーラム有識者委員および水産資源分科会座長(2023年〜現在)
・水産庁 太平洋広域漁業調整委員会 委員(2018年〜現在)
・水産庁 水産流通適正化推進会議 委員(2024年)
他
- 資料ダウンロード
日韓欧米、そして世界でIUU漁業対策の実効性を高めるには
IUU漁業対策の要となる水産物輸入管理制度。EU、米国などの制度に関する調査報告書が2019年に欧州のNGOらによって発表されたことは日韓の制度新設を後押ししましたが、今年新たに出された報告書では日韓の制度も評価の対象に加わりました。この新報告書の筆者の一人をお招きし、既存の水産物輸入管理制度の実効性を世界で高めるとともに、制度を新設する国との連携を強化するために不可欠な次のステップについて議論します。
パネリスト
-
トム・ウォルシュ
EU IUU連合
コーディネーターEU IUU連合
コーディネータートム・ウォルシュ
トム・ウォルシュは、EU IUU漁業連合のコーディネーターを務めている。この連合では、違法・無報告・無規制(IUU)漁業をなくすため、世界の漁業の透明性とガバナンスの改善においてEUのリーダーシップを推進することを目的に、複数の非政府組織が協力して活動している。
トムは、EU IUU漁業連合のリサーチャーを務め、IUU漁業問題、漁業の透明性、シーフードのトレーサビリティに関する多様なテーマについて数多くの報告書を発表してきた。
エディンバラ大学で海洋システムと政策の修士号を、シェフィールド大学で生物学の学士号を取得している。 -
マックス・バレンタイン
オセアナ
キャンペーン・ディレクター兼シニア・サイエンティストオセアナ
キャンペーン・ディレクター兼シニア・サイエンティストマックス・バレンタイン
マックス・バレンタイン博士は、アメリカにおけるオセアナの違法漁業および透明性キャンペーンのキャンペーン・ディレクター兼シニア・サイエンティスト。15年にわたる研究経験を有し、その知見を活かして、漁業の透明性と水産物のトレーサビリティを拡大することにより、IUU(違法・無報告・無規制)漁業との闘いにおいてオセアナの取り組みを主導している。また、世界各地における違法漁業の事例に関する調査を実施するデータ分析チームの監督も務めている。
-
古川 智香子
水産庁
漁政部加工流通課
水産流通適正化推進室長水産庁
漁政部加工流通課
水産流通適正化推進室長古川 智香子
平成18年に農林水産省に入省。消費・安全局、経営局、生産局、大臣官房検査・監察部、林野庁、内閣府食品安全委員会事務局への出向を経て、2024年7月より現職。
-
イ・ジュヨン
韓国海洋水産部
遠洋漁業課
政策アナリスト韓国海洋水産部
遠洋漁業課
政策アナリストイ・ジュヨン
イ・ジュヨンは、韓国海洋水産省遠洋漁業部で政策アナリストを務めている。入省後、海洋および漁業の多岐にわたる分野で国際協力を推し進める業務に携わり、同省でのキャリアをスタートさせた。この時の経験から、地球規模の問題に対処するための協調的対応に関する貴重な見識を得た。現在は、各地域や国内外のステークホルダーと協力し、政府の政策をより効果のあるものにする取り組みや、持続可能な漁業と海洋環境にとって大きな脅威となるIUU漁業と闘う国際的な取り組みの支援に尽力している。
モデレーター
-
植松 周平
WWFジャパン(公益財団法人 世界自然保護基金ジャパン)
自然保護室 海洋水産グループ
IUU漁業対策マネージャー 兼 水産資源管理マネージャーWWFジャパン(公益財団法人 世界自然保護基金ジャパン)
自然保護室 海洋水産グループ
IUU漁業対策マネージャー 兼 水産資源管理マネージャー植松 周平
東京大学大学院農学生命科学研究科博士課程修了。学位取得後、経営コンサルティング会社アクセンチュアを経て、国際水産資源研究所(現 水産研究・教育機構)に入所。太平洋クロマグロの資源研究を行う。
2013年よりWWFジャパンで勤務し、マグロ、カツオ、サンマ、イカなどの国際水産資源の保全やIUU漁業対策に関わる業務に従事。2021年および2024年に、水産庁の水産流通適正化法検討委員を務めた。
水産業における人権侵害と企業に求められる対策と責任
世界の水産供給を支える現場では、今もなお深刻な人権侵害が発生しています。本セッションでは、東南アジアを例に現場での労働搾取や強制労働の実情と、企業による人権アセスメントの実効性、マグロ業界で明らかになった人権侵害の事例とそれに対する企業の取り組み、そして、企業が国に対して求める法制度や規制のあり方について、事例と実務の両面から掘り下げ、参加者とともに解決の方向性を考えます。
パネリスト
-
ザカリ・エドワーズ
グローバル・レイバー・ジャスティス
シニア・シーフード・キャンペーン・コーディネーターグローバル・レイバー・ジャスティス
シニア・シーフード・キャンペーン・コーディネーターザカリ・エドワーズ
ザカリ・エドワーズは、水産業界における労働者の権利問題に関して豊富な経験を有する専門家である。過去の職務においては、ツナ(マグロ)サプライチェーンにおける社会的責任改善の実施を統括し、市場関係者、NGO、アドボカシー団体を効果的にリードし、世界の漁業産業における説明責任の強化に寄与してきた。
現在、ザカリはグローバル・レイバー・ジャスティスにおいてシーフード・キャンペーン上級コーディネーターを務めている。この役割では、パートナー労働組合や労働者団体の強化を推進し、企業および政府の説明責任を確保するとともに、水産サプライチェーンにおける労働および人権保護のための取り組みを主導している。
また、ザカリは水産業界における労働権擁護の豊富な経験と知見を活かし、「シーフード・ワーキング・グループ(Seafood Working Group, SWG)」のコーディネーターも務めている。SWGは30以上の非営利団体、そのサブグループおよび諮問委員会で構成される国際的な連携組織であり、ザカリはプログラム目標達成に向けた計画の策定と実施を統括している。
さらに、ザカリは現在、「コンサベーション・アライアンス・フォー・シーフード・ソリューション(Conservation Alliance for Seafood Solutions, CASS)」の理事も務め、水産分野における持続可能性と労働者の権利保護を推進している。 -
アフメッド・ムドザキル
フォーラム・シラトラミ・ペラウト・インドネシア(FOSPI)
フォーラム・シラトラミ・ペラウト・インドネシア(FOSPI)
アフメッド・ムドザキル
アフメッド・ムドザキルは、台湾・東港を拠点とするインドネシア出身の移住労働者であり、労働者の権利擁護における主要な活動家である。漁業および水産加工業界における20年以上の経験を有し、移住漁業労働者の組織化、エンパワーメント、権利擁護に生涯を捧げてきた。
2015年以降、ムドザキルは台湾沿岸・深海商業漁業に従事する出稼ぎ漁民のために労働・生活条件改善を求めて闘う自主組織団体「フォーラム・シラトラミ・ペラウト・インドネシア(FOSPI)」の中心的リーダーを務めている。彼の指導のもと、FOSPIは2,300人以上の会員を擁する草の根労働組合へと成長し、2022年には正式に「ピングタング・マイグラント・フィシャーズ・ユニオン(Pingtung Migrant Fishers Union)」として登録された。彼は、公正な賃金の実現や、海上におけるWi-Fiの必須提供を勝ち取るなど、移住漁業労働者の労働環境改善に向けたキャンペーンを成功へ導いた。
また、ムドザキルは、地域初となるモスク「アンヌール・モスク」を屏東県に設立するうえでも重要な役割を果たした。同モスクは、長年にわたる草の根レベルでの資金調達と地域社会の協力によって建設されたものである。これらの貢献により、ムドザキルが率いる組織は数多くの表彰を受けており、その中には、在外インドネシア国民保護への献身が評価されたインドネシア外務省による「ハッサン・ウィラジュダ賞」も含まれる。
ムドザキルは現在も、台湾、インドネシア、さらに日本、米国、欧州を含む主要な水産物市場国において、政府、NGO、労働組合、アドボカシーネットワークとの連携を通じ、移住労働者の権利擁護活動を継続している。 -
松本 哲
日本生活協同組合連合会
ブランド戦略本部サステナビリティ戦略室日本生活協同組合連合会
ブランド戦略本部サステナビリティ戦略室松本 哲
1988年 日本生活協同組合連合会入職、物流管理、商品営業、商品開発・企画などCO・OP商品(PB)事業に関わる業務を経験。 2010年~ 共同開発推進部部長、2012年~ 東北支所支所長、2014年~ 水産部部長、2016年~ 生鮮原料事業推進室室長、2017年7月~ 商品本部・本部長スタッフ。2022年1月~ 現職
-
ウィリアム・グティエレス・ラガマット
ディグニティー・イン・ワーク・フォー・オール
シニア・法律・政策アドバイザーディグニティー・イン・ワーク・フォー・オール
シニア・法律・政策アドバイザーウィリアム・グティエレス・ラガマット
ウィリアム・グティエレス・ラガマットは弁護士、政策コンサルタント、公認社会的コンプライアンス監査人/評価者の資格を持ち、大学での教育やジャーナリズム活動を含め、合わせて20年以上の職業経験を持つ。官民両部門に携わり、フィリピン財務省には腐敗防止イニシアティブに基づく法的・規制的要件に関する技術支援を、政府調達政策委員会-技術支援室にはその一部門を管理し、官民の利害関係者に調達法に関する法的・技術的支援を提供している。
2003年以来、国際労働権利団体ディグニティー・イン・ワーク・フォー・オール(Dignity in Work for AllまたはDIWA、旧名Verité Southeast AsiaまたはVSEA)に関与。現在はDIWAのシニア・リーガル・アンド・ポリシー・アドバイザーを務め、水産・農業、製造業、物流、サービス業、接客業など、世界各地の産業における監査・評価を主導している。DIWAのシニア・トレーニング・ファシリテーターの一人として、オーストラリア、日本、東南アジア、その他の地域において、サプライチェーン・マネジメントにおける規制や国際的なベストプラクティス基準の遵守について、民間および政府関係者にトレーニングを提供している。
エジンバラ大学国際商法・実務法修士候補。フィリピン大学で法学博士号(法学)を取得。同大学でジャーナリズムの学士号も取得。
モデレーター
-
小川 隆太郎
認定NPO法人ヒューマンライツ・ナウ
事務局長認定NPO法人ヒューマンライツ・ナウ
事務局長小川 隆太郎
弁護士。労働事件、行政訴訟事件、入管・難民事件などを専門とする。2022年より認定NPO法人ヒューマンライツ・ナウ(HRN)事務局長。その他、国際人権法学会理事、日本弁護士連合会国際人権条約WG自由権規約担当事務局次長、全国難民弁護団連絡会議 世話人などを務める。
- 資料ダウンロード
気候危機時代ー国際水域における水産資源管理はどうあるべきか
気候危機が海洋生態系に大きな変化をもたらしています。種の分布の変化や、バイオマスや生産性の大幅な減少が予測されており、海洋生態系、水産業、地域社会にこれまで以上に大きな影響を及ぼすことは必至です。気候変動の影響を踏まえ、公海、排他的経済水域(EEZ)を含めた国際水域における水産資源管理はどうあるべきか、有識者で議論します。
パネリスト
-
宮原正典
農林水産省顧問
よろず水産相談室afc.masa代表農林水産省顧問
よろず水産相談室afc.masa代表宮原正典
水産庁に37年勤務し2014年に退職し、その後水産研究・教育機構理事長として7年間勤務し、2021年に退職。
20代の終わりに米国デューク大学に留学した後、多くの国際交渉に従事し、特にクロマグロ関係の国際会議で議長を務めるなど活躍、現在も中西部太平洋マグロ類保存委員会の太平洋クロマグロを担当する北委員会議長を務めている。また東日本大震災の発生から水産庁の復興チームのリーダーとして、救援活動から水産業復興まで一貫して働いた。
現在は、afc.masa代表として、水産業に関わる様々な問題の相談に乗るため国内外を飛び回り活動している。 -
トランスフォーム・アコラウ教授
ソロモン諸島国立大学
学長室
学長ソロモン諸島国立大学
学長室
学長トランスフォーム・アコラウ教授
トランスフォーム・アコラウ教授は、ソロモン諸島国立大学の学長を務める、太平洋地域における海洋ガバナンス、漁業管理、海洋資源の持続可能な利用に関する法・政策の第一人者である。これまでに、太平洋諸島フォーラム漁業機関(FFA)、ナウル協定締約国(PNA)、ソロモン諸島政府などで上級顧問として要職を歴任し、地域協力によるまぐろ資源管理の推進において重要な役割を果たしてきた。
また、インド太平洋地域における気候変動と海洋政策・ガバナンスの連携に関する分野でも、先導的な発信を行っている。国際法の博士号をウーロンゴン大学で取得し、漁業法、海洋外交、太平洋地域主義に関する著作も多数ある。高等教育機関が持続可能な開発や気候レジリエンスに積極的に貢献することの重要性を、深く信じて活動している。 -
フセイン・シナン
モルディブ共和国 漁業・海洋資源省
漁業・海洋資源管理局
ディレクター・ジェネラルモルディブ共和国 漁業・海洋資源省
漁業・海洋資源管理局
ディレクター・ジェネラルフセイン・シナン
シナンは過去7年間にわたり、インド洋まぐろ類委員会(IOTC)においてモルディブを代表し、IOTC財務・管理常設委員会の議長、G16沿岸国グループの共同議長、南西インド洋漁業委員会(SWIOFC)の議長など、重要なリーダーシップを担ってきた。複数の地域漁業管理機関(RFMO)および地域漁業機関(RFB)に積極的に関与し、BBNJ(国家管轄権外区域における海洋生物多様性)協定交渉ではモルディブの首席交渉官を務めた。また、日本財団オーシャン・ネクサスプログラムを通じてカナダのダルハウジー大学にてポスドク研究員を務め、特にインド洋におけるRFMOの強化をテーマに研究を行った。近年では、みなみまぐろ保存委員会(CCSBT)および南インド洋漁業協定(SIOFA)のパフォーマンスレビュー委員会の議長も務めている。現在は、次世代のRFMOに関する書籍の出版に向け、UBCプレスとの協働を進めている。
モデレーター
-
クエンティン・ハニッチ
ウーロンゴン大学
オーストラリア国立海洋資源安全保障センター(ANCORS)
教授・漁業ガバナンスプログラムリーダーウーロンゴン大学
オーストラリア国立海洋資源安全保障センター(ANCORS)
教授・漁業ガバナンスプログラムリーダークエンティン・ハニッチ
クエンティン・ハニッチ教授は、ウーロンゴン大学のオーストラリア国立海洋資源安全保障センター(ANCORS)において、日本財団オーシャン・ネクサス・チェアを務めるとともに、水産ガバナンス研究プログラムを主導している。
ハニッチ教授は、インド太平洋地域を中心に、海洋ガバナンスや新興技術、海洋保全、水産資源の管理および開発に関する国際的な研究パートナーシップに広く携わってきた。国際委員会や作業部会の議長を務めたほか、政府間ワークショップのファシリテーターや、閣僚会合および各国代表団への助言者としての実績も有する。
ウーロンゴン大学での活動に加え、インド洋まぐろ類委員会(IOTC)における「配分基準に関する技術委員会」の議長、日本財団オーシャン・ネクサス・プログラムの主任研究者を務める。また、日本の水産研究・教育機構、韓国海洋研究院(KMI)、グローバル・フィッシング・ウォッチ、ソロモン諸島国立大学などと研究連携を行っている。
小規模漁業の未来を描くーDXとサステナブル金融の力
東・東南アジアにおいて、食料安全保障や地域経済維持の観点から重要な役割を持つ小規模漁業の重要性が高まる一方、その脆弱性が課題になっています。小規模漁業の持続可能性、さらにはその特長である多様性をいかに高めていくか。デジタルトランスフォーメーション(DX)とサステナブルファイナンスを両輪に、小規模漁業とその地域社会を活性化させるための道筋を議論します。
パネリスト
-
津田 祐樹
株式会社フィッシャーマン・ジャパン・マーケティング
代表取締役社長株式会社フィッシャーマン・ジャパン・マーケティング
代表取締役社長津田 祐樹
宮城県石巻市の仲卸2代目であったが、東日本大震災を機に地元漁師らと一般社団法人フィッシャーマン・ジャパンを設立。
現在は販売部門を株式会社フィッシャーマン・ジャパン・マーケティングとして分社化し、国内外への販路拡大や全国の漁村支援を推進。その傍らで「海洋環境保全」「IUU撲滅」「資源管理推進」を目指し、サステナブルシーフードの普及啓蒙、FJブルーファンドによるインパクト投資、志の高い全国の漁業者・水産関係者と共に『水産未来サミット』を主宰し、現場の声を国に届ける政策提言活動にも取り組んでいる。 -
粂井 真
UMINEKOサステナビリティ研究所
代表UMINEKOサステナビリティ研究所
代表粂井 真
北海道札幌市出身。2002年〜2013年農林水産省勤務。退職後、民間企業にて農林水産ビジネス、環境政策等に関するコンサルティングに従事した後、2021年にUMINEKOサステナビリティ研究所を設立。水産資源の回復と持続可能な漁業振興に向けたフォーラムの運営等を担う。
直近では、水産関係の幅広いステークホルダーが組織の立場を越えて議論を行うチャタムフィッシュの事務局として、急速に進む海洋環境の変化に対して、漁業分野で必要な対策の取りまとめを実施。 -
狭間 拓人
古野電気株式会社
舶用機器事業部
DX推進部 水産DX推進課
課長古野電気株式会社
舶用機器事業部
DX推進部 水産DX推進課
課長狭間 拓人
2010年に古野電気へ入社し、舶用無線機や漁船向け魚群探知機の研究開発に従事してきました。魚群探知機の開発をする中では、音響データを活用した操業の振り返りや後継者育成、船団での情報共有など、漁業を支えるデータソリューションの開発を推進。現在は魚群探知機以外のデータも活用し、海洋環境予測や水産資源推定など、水産社会の発展に貢献する企画・PoC・開発に取り組んでいます。
-
小林 正典
笹川平和財団
上席研究員笹川平和財団
上席研究員小林 正典
笹川平和財団(SPF)上席研究員。SPF特任部長、SPF海洋政策研究所(OPRI)上席研究員等を経て現職。持続可能なブルーエコノミー、海洋環境・資源管理、持続可能な漁業、海洋汚染対策、海洋再生可能エネルギー、地域・国際協力・パートナーシップなど、海洋と持続可能性に関する政策研究を行う。海洋政策研究財団、横浜国立大学、地球環境戦略研究機関、国連(ニューヨーク、ジュネーブ、ボン)、外務省ニューヨーク国連政府代表部で持続可能性課題に関する研究・職務に従事。主な著作物に、小林正典(2024)「国家管轄権外区域の海底鉱物資源と太平洋島嶼国—拮抗する利害と国際協調に向けた課題—」『日本海洋政策学会誌』第13号50-64頁やKobayashi, M. et al (2022) Capitalizing on Co-Benefits and Synergies to Promote the Blue Economy in Asia and the Pacific”. In: Morgan, P. et al. eds. Blue Economy and Blue Finance – Toward Sustainable Development and Ocean Governance. Asian Development Bank Institute, pp. 150 – 189などがある。2025年2月のホニアラ持続可能な漁業サミット、気候変動締約国会議オーシャンパビリオン、NIKKEIブルーオーシャン・フォーラム、世界海洋サミット(2023年-2024年)、パナマでの私たちの海洋会議(2023年)、パラオでの私たちの海洋会議(2022年)等、各種国際会議で発表を行ってきている。
-
マーティン・パーベス
インターナショナル・ポール・アンド・ライン・ファウンデーション(IPNLF)
専務取締役インターナショナル・ポール・アンド・ライン・ファウンデーション(IPNLF)
専務取締役マーティン・パーベス
マーティン・パーベスは、水産管理およびステークホルダー・エンゲージメントの専門家であり、現場、政府、コンサルタント業務、市場、非営利セクターにおいて20年以上の経験を有する。2016年より、インターナショナル・ポール・アンド・ライン・ファウンデーション(International Pole and Line Foundation / IPNLF)の専務取締役として、その活動を主導している。
キャリアの出発点は漁船上の漁業オブザーバーであり、その後は科学調査航海のリーダーとしても乗船し、南氷洋、インド洋、大西洋、太平洋において、大小さまざまな漁船で約4年間を過ごした経験を持つ。南アフリカ水産省では資源管理官として勤務し、RFMO(カツオ・マグロ類の地域漁業管理機関)会議において自国代表を務めた。また、政府機関での科学者および管理者としての勤務の合間には、MRAGおよびCapfishにて漁業コンサルタントとして従事した。その後、MSC(海洋管理協議会)の南部アフリカ・プログラムを立ち上げ、7年間にわたり同プログラムを率いた。マーティンが「これまでで最も過酷な仕事」と語るのは、南極海で漁師として働いた経験である。
モデレーター
-
花岡 和佳男
株式会社シーフードレガシー
創立者 / 代表取締役社長株式会社シーフードレガシー
創立者 / 代表取締役社長花岡 和佳男
フロリダの大学にて海洋環境学および海洋生物学を専攻。卒業後、モルディブおよびマレーシアにて海洋環境保全事業に従事。2007年より国際環境NGOの日本支部でサステナブルシーフード・プロジェクトを企画・牽引。
独立後、2015年に東京でシーフードレガシーを創立し、CEOに就任。「海の自然・社会・経済のつながりを象徴する水産物(シーフード)を豊かな状態で未来世代に継ぐ(レガシー)」ことをパーパスに、境持続性および社会的責任が追求された水産物をアジア圏における水産流通の主流にすべく、システムチェンジを牽引。
2019年には SeaWeb Seafood Champion Award リーダーシップ部門でチャンピオンを受賞。先見性のあるビジョンと、国内外の水産業界、金融機関、政府、NGO、アカデミア、メディアなど、多様なステークホルダーをつなぐ、その卓越したリーダーシップにより、アジアの水産業界における革新的なリーダーとして注目されている。
・IUUフォーラムジャパン メンバー(2017年〜現在)
・G1海洋環境研究会アドバイザリーボードメンバー(2018年〜現在)
・世界経済フォーラム フレンズ・オブ・オーシャン・アクション メンバー(2021年〜現在)
・コアリション・フォー・フィッシャリー・トランスパレンシー 理事(2022年〜現在)
・コンサベーション・アライアンス・フォー・シーフード・ソリューション 理事(2023年〜現在)
・NIKKEIブルーオーシャン・フォーラム有識者委員および水産資源分科会座長(2023年〜現在)
・水産庁 太平洋広域漁業調整委員会 委員(2018年〜現在)
・水産庁 水産流通適正化推進会議 委員(2024年)
他
- 資料ダウンロード
新潮流ー日本の水産企業による非競争連携がもたらすインパクト
サステナビリティを実践する企業にとって課題が多い環境デューデリエンス、人権デューデリエンス、トレーサビリティの3分野において、個別企業だけでは解決が困難な問題をコレクティブな体制のもとで解決するための取り組みが日本でも始まっています。水産物を取り巻く国際的課題を中長期的に解決し、インパクトを生み出すには、実効性ある協働体制の確立が必須です。このセッションでは、日本企業が実効性ある協働を実施する上で必要な「手引き」を紹介し、非競争連携のあり方を含めた取り組みの方向性を議論します。
パネリスト
-
カルメン・ゴンザレス-ヴァレス
サステナブル・フィッシャリーズ・パートナーシップ(SFP)
サプライチェーンラウンドテーブル
ディレクター(イカ、タコ類)サステナブル・フィッシャリーズ・パートナーシップ(SFP)
サプライチェーンラウンドテーブル
ディレクター(イカ、タコ類)カルメン・ゴンザレス-ヴァレス
カルメン・ゴンザレス-ヴァレスはビーゴ大学で海洋科学の学位を取得し、水産資源の経済、管理、評価に関する修士号を有する。2016年よりSFP(Sustainable Fisheries Partnership)に所属し、当初はマーケッツチームにて、Aldiやディズニーをはじめとする国際的なブランド、小売業者、フードサービス企業、HORECA(ホテル・レストラン・カフェ)チャネルの企業との連携を担当してきた。
2021年以降は、SFPにおける役割として、頭足類(タコ類など)漁業の改善促進、IUU(違法・無報告・無規制)漁業および人権侵害への対策、水産物サプライチェーン全体における責任ある調達の推進を担っている。
SFP以前は、世界各地で漁業オブザーバーとしての豊富な経験を積み、インド洋まぐろ委員会や欧州漁業管理機関などで初期のキャリアを築いた。 -
馬渕 悠人
株式会社セブン&アイ・ホールディングス
セブンプレミアム開発戦略部
生鮮マーチャンダイザー株式会社セブン&アイ・ホールディングス
セブンプレミアム開発戦略部
生鮮マーチャンダイザー馬渕 悠人
セールスプロモーション、ブランディング会社での勤務を経て現職。
ブランディング会社では養殖魚のブランディングを担当し、全国の養殖生産者を周り安全安心で高品質のPBとしてイトーヨーカドーで販売。現在はセブンイレブンやイトーヨーカドーなどで販売している「セブンプレミアム」の開発事務局として水産カテゴリの持続可能な商品開発に注力している。 -
佐藤 雄介
マルハニチロ株式会社
サステナビリティ戦略部
部長マルハニチロ株式会社
サステナビリティ戦略部
部長佐藤 雄介
1994年マルハ株式会社(現マルハニチロ株式会社)に入社。海外事業部門でマダガスカルのエビ漁業・養殖合弁会社管理、輸出入・エビ販売業務等に15年間従事した。
2009年よりの水産部門を中心にマルハニチログループの品質保証・品質管理部門で製造工場の品質・衛生管理、監査等を担当し、2020年4月よりサステナビリティ推進に従事し、2025年4月より現職
モデレーター
-
山内 愛子
株式会社シーフードレガシー
取締役副社長株式会社シーフードレガシー
取締役副社長山内 愛子
東京水産大学資源管理学科卒業。東京海洋大学大学院博士課程修了。海洋科学博士。日本の沿岸漁業における資源管理型漁業や共同経営事例などを研究した後、WWFジャパン自然保護室に入局。持続可能な漁業・水産物の推進をテーマに国内外の行政機関や研究者、企業関係者といったステークホルダーと協働のもと水産資源および海洋保全活動を展開。2019年にシーフードレガシーに入社。国内NGO等の連携である「IUU漁業対策フォーラム」のコーディネーターを務める。
サプライチェーンの「見える化」で導く、新たな資金調達
水産関連企業が、投融資機関から求められる環境や人権に関する情報開示に応えるには、フルチェーントレーサビリティの構築が欠かせません。いかにサプライチェーン全体可視化することで、IUU漁業や人権侵害等のリスクを排除し、サステナブルファイナンスを呼び込むか、有識者で議論します。
パネリスト
-
マックス・ブッシェー
FAIRRイニシアチブ
生物多様性・海洋研究
自然・海洋プログラム統括責任者FAIRRイニシアチブ
生物多様性・海洋研究
自然・海洋プログラム統括責任者マックス・ブッシェー
マックス・ブッシェーは、2021年よりFAIRRの自然・海洋プログラム統括責任者を務め、これらのテーマに関する投資家ネットワークの調査やエンゲージメントを統括している。FAIRRに参画する前は、ブルームバーグ(主にブルームバーグ・インテリジェンスのリサーチグループ)で8年間勤務していた経験を持つ。株式調査アナリストを務めたのち、関心領域はESGやサステナブルファイナンスへと移った。HECモントリオールで金融学を学んだマックスは、CFA資格保有者でもある。
-
ヒュー・トーマス
グローバル・ダイアログ・オン・シーフード・トレーサビリティ
エグゼクティブ・ディレクターグローバル・ダイアログ・オン・シーフード・トレーサビリティ
エグゼクティブ・ディレクターヒュー・トーマス
ヒュー・トーマスは、シーフード加工業者、小売業者、非政府組織に対して、責任ある調達やサプライチェーンに関する助言を提供するため、2020年に3 Pillars Seafoodを設立した。
シーフード業界で約30年のキャリアを持ち、イギリスの小売業者で水産・養殖マネージャーを務め、違法漁業撲滅を目指す米国の信託で市場連携業務を主導、イギリスの主要なチルドシーフード加工会社でテクニカルディレクターを務め、ベトナムでエビ加工工場を運営した経験もある。
また、グローバル・ダイアログ・オン・シーフード・トレーサビリティ(GDST)においては、エグゼクティブ・ディレクターとして組織を率い、世界中で普遍的に採用されるデジタル・トレーサビリティが、水産業および養殖業のサプライチェーンにおける信頼を促進するというビジョンの実現を目指している。 -
末吉 光太郎
みずほフィナンシャルグループ 兼 みずほ銀行
サステナブルビジネス部
GCSuO補佐(サステナビリティ&インパクト)みずほフィナンシャルグループ 兼 みずほ銀行
サステナブルビジネス部
GCSuO補佐(サステナビリティ&インパクト)末吉 光太郎
みずほ銀行入行後、大企業法人営業、国際業務・国内法人業務企画部門等を経て法人向けサステナブルビジネス企画を担当。22年9月からサステナブルビジネス部 副部長に着任。
GSG Impact JAPAN 委員、インパクト志向金融宣言 運営委員、インパクトコンソーシアム データ・指標分科会副座長 等 -
和田 健
三井住友トラスト・アセットマネジメント
スチュワードシップ推進部
シニア・スチュワードシップ・オフィサー三井住友トラスト・アセットマネジメント
スチュワードシップ推進部
シニア・スチュワードシップ・オフィサー和田 健
三井住友信託銀行に入社後、資産運用業務に従事。日本株式アナリストを経て、米国・ニューヨーク及び英国・エディンバラに駐在、提携運用機関にてアナリスト業務を担当。
2017年よりシニア・スチュワードシップ・オフィサーとして、外国企業に対するエンゲージメントと議決権を担当。現在、英国NGO・SPOTTのテクニカル・アドバイザリーグループ・メンバー。Net Zero Asset Managers initiative (気候変動) 及び PRI・Spring(自然資本) のアドバイザリーグループを兼務。
米国公認会計士(米・デラウェア州) -
河口 眞理子
立教大学
社会デザイン研究科
特任教授立教大学
社会デザイン研究科
特任教授河口 眞理子
大和証券グループ本社CSR室長、大和総研研究主幹など歴任。2020年4月より現職。企業の立場(CSR)投資家の立場(ESG投資)生活者の立場(エシカル消費)のサステナビリティ全般に関し20年以上調査研究、提言活動に従事。現職では、サステナビリティ学についての教育にかかわる傍ら、相模屋食料株式会社CEOアドバイザーとして食の持続可能性にもかかわる。またアセットマネジメントOneサステナビリティ諮問会議アドバイザー、三菱化工機社外取締役もつとめる。
モデレーター
-
藤田 香
東北大学グリーン未来創造機構・大学院生命科学研究科教授、兼、日経ESGシニアエディター
東北大学グリーン未来創造機構・大学院生命科学研究科教授、兼、日経ESGシニアエディター
藤田 香
富山県魚津市生まれ。東京大学理学部物理学科卒。日経BPに入社し、日経エレクトロニクス記者、ナショナルジオグラフィック日本版副編集長、日経エコロジー編集委員、日経ESG経営フォーラムプロデューサー、日経ESGシニアエディターなどを歴任。生物多様性や自然資本、持続可能な調達、ビジネスと人権、ESG投資、地方創生などを専門とする。東北大学教授として「ネイチャーポジティブ発展社会実現拠点」の副拠点長を務める。環境省中央環境審議会委員。地球環境戦略研究機関(IGES)理事。NIKKEIブルーオーシャン有識者委員会共同座長。近著に『ESGとTNFD時代のイチから分かる生物多様性・ネイチャーポジティブ経営』などがある。
- 資料ダウンロード
世界が求める水産物、拡大する水産物需要と輸出の壁
日本産の水産物は、その品質と安全性から世界各国で注目を集め、需要が拡大し続けています。一方で、実際に海外市場へ輸出するには、国際的に求められるサステナビリティやトレーサビリティ(流通履歴の透明性)への対応が重要な課題となっています。本セッションでは、行政、業界による水産物輸出政策、地域連携による日本産水産物の海外輸出の取り組み、そして海外市場が求めるサステナビリティとトレーサビリティ要件について取り上げます。これらをテーマに、最新の情報と実務上のポイントを共有し、日本の水産業が世界市場で持続的に成長するための道筋を探ります。
パネリスト
-
髙瀨 美和子
一般社団法人 大日本水産会
専務理事一般社団法人 大日本水産会
専務理事髙瀨 美和子
1984年に農林水産省に入省し、水産専門職として主として水産庁で従事してきた。漁場資源課長、研究指導課長、資源管理部審議官を歴任し、2023年農林水産省退職、2023年11月より現職。
-
岸 克樹
Wismettac フーズ 株式会社
フードセーフティマネジメント部
執行役員Wismettac フーズ 株式会社
フードセーフティマネジメント部
執行役員岸 克樹
大手ビールメーカー、大手小売チェーンを経て、2024年にWismettacフーズ株式会社へ入社。メーカー、小売、中間流通それぞれの立場で品質管理を経験し、特に小売チェーンでは、多カテゴリーにわたるプライベートブランド商品の品質保証を統括した。
現職では、欧米を中心とした輸出適法管理および食品安全管理を統括している。
これまでに政府委員やGFSI(Global Food Safety Initiative)国際委員を歴任。GFSIでは、国際標準の国内普及や、国内規格の国際標準化などを実現し、食品流通における国際ハーモナイゼーションに関する知見を豊富に有する。
・2016年~2018年 食品表示部会委員(内閣府)
・2016年~2018年 日本農林規格調査会委員(農林水産省)
・2014年~2018年 GFSI(Global Food Safety Initiative)国際委員
・2014年~2018年 GFSI 日本ローカルグループ議長 -
久米 尚
あづまフーズ株式会社
販売事業本部 東京支店
東京支店長あづまフーズ株式会社
販売事業本部 東京支店
東京支店長久米 尚
1998年、米国あづまフーズに入社。米国市場での営業活動を通じて実践的なビジネス経験を積んだ後、日本本社の海外事業部に転籍。以降、東南アジア地域の市場開拓を担当し、現地の食文化やニーズに寄り添ったビジネス展開に尽力してまいりました。
特に市場開拓の初期段階では、ゼロからのスタートで開発に取り組み、商品開発の根幹を支える「原料ソース」の重要性を現場で体感。サステナビリティの視点からも、持続可能な調達や地域との共創の在り方について深い知見を得ました。
現在は、これまで培った海外での経験と視点を国内市場に還元し、グローバルな視野での価値創出を目指しています。 -
マイケル・マクニコラス
オディシー スーパーフローズン LLC
代表取締役社長オディシー スーパーフローズン LLC
代表取締役社長マイケル・マクニコラス
マイケルは2016年にグループを設立し、北米におけるテイクアウト寿司の品質向上を目指している。2025年には、カリナリー・コラボレーションズLLCとカリマー USA LLCが統合され、オディシー スーパーフローズン LLCが設立された。同社は、マグロ、サーモン、エビ、ハマチなどを含むスーパーフローズン食材の開発・流通を担い、日本、ニュージーランド、ベトナム、韓国、ノルウェー、カナダ、インドネシア、フィジーといった世界各国の優良生産者から調達している。マイケルは、北米全域の主要寿司事業者に向け、ナチュラルで持続可能かつトレーサブルな高品質食材を提供する専門チームを率いている。
彼は食品安全を強く重視し、第三者認証の推進に尽力している。そのリーダーシップのもと、オディシー スーパーフローズンはGFSI認証およびMSC/ASC CoC(Chain of Custody)認証を取得し、製品が世界的に認められた最高水準の食品安全・品質基準に準拠していることを保証している。
起業家としての活動にとどまらず、業界全体の取り組みにおいても主導的役割を担っている。2023年には、北米の急成長する寿司産業におけるニーズや機会に先進的に対応するため、業界の主要ステークホルダー間で協働とイノベーションを促進する全米水産協会(NFI)寿司協議会を設立し、初代会長に就任した。さらに、世界的な水産物トレーサビリティ推進組織であるGDST(グローバル ダイアログ オン シーフード トレーサビリティー)の監督委員会会長も務め、国際的なメンバーと連携しながら水産物のトレーサビリティ向上に取り組んでいる。
モデレーター
-
孫 凱軍
株式会社シーフードレガシー
企画営業部
チーフ株式会社シーフードレガシー
企画営業部
チーフ孫 凱軍
大手水産商社で、水産原料の輸入・加工・販売ほか、海外駐在も経験。グローバルな水産流通の最前線で実務を積み、その後、外資系水産企業にてサーモン商材の営業を担当。現在は、水産業界におけるサステナビリティの専門家として水産企業のサステナビリティの推進や日本産サステナブル・シーフードの市場拡大を支援している。水産流通と水産サステナビリティの両分野に精通し、水産企業の変革を促すアドバイザリー業務に従事している。
- 資料ダウンロード
責任ある養殖飼料調達で拓く養殖の未来
デジタルトランスフォーメーション(DX)化や大規模陸上養殖により、世界的に拡大を続ける水産養殖。その持続可能な発展には、養殖域の環境保全や人権配慮だけでなく、環境や水産資源に配慮した責任ある飼料の調達が必要不可欠です。本セッションでは、責任ある調達に取り組む企業や、飼料の基準を定める認証団体と共に、養殖飼料の調達実践を中心に、持続可能な養殖の推進について議論します。
パネリスト
-
徳井 貞仁
スクレッティング株式会社
マーケティング本部
ディレクタースクレッティング株式会社
マーケティング本部
ディレクター徳井 貞仁
早稲田大学で工学修士号を取得後、グロービス経営大学院にてMBA(経営学修士)を取得。
様々な業界にて事業開発やマーケティング戦略の立案/推進に携わり、2024年12月にスクレティング株式会社のマーケティング責任者として就任。
イノベーションを通じたサステナブルな養殖の実現に向けて奮闘中。登壇プログラム -
バーバラ・ユンカー
水産養殖管理協議会(ASC)
市場開発
欧州&アジア太平洋コマーシャル・ディレクター水産養殖管理協議会(ASC)
市場開発
欧州&アジア太平洋コマーシャル・ディレクターバーバラ・ユンカー
バーバラ・ユンカーは現在、水産養殖管理協議会(ASC)にて、欧州&アジア太平洋コマーシャル・ディレクターを務めている。2015年にASCに入社して以来、市場開発部およびマーケティング&コミュニケーション部においてさまざまな役職を歴任してきた。養殖水産物のサプライチェーンに関する重要な課題に対し、協働的な解決策を見出すことに情熱を注いでいる。
オーストリア出身のバーバラは、ウィーン大学でジャーナリズムとマーケティングを学び、その後、英国のウォーリック・ビジネス・スクールにて企業の社会的責任(CSR)と持続可能性に焦点を当てた経営学修士(MBA)を取得した。民間企業およびコンサルティング業界でマーケティングと広報の職を経験した後、15年以上前にNGOの世界へと活動の場を移した。
ASCに入る前には、世界自然保護基金(WWF)で5年間勤務し、東欧における企業パートナーシップの分野を担当した後、WWFオーストリアにて「持続可能な食」のテーマを立ち上げた。また、タイにも派遣され、現地チームの市場変革活動を支援した。登壇プログラム -
フランシスコ・アルドン
マリントラスト
CEOマリントラスト
CEOフランシスコ・アルドン
フランシスコは、海産原料に関する主要な認証プログラムであるマリン・トラストにおいて、IFFO(海洋原料機構)内での初期開発段階から携わってきた。2020年よりマリン・トラストのCEOを務めている。食品分野で15年以上の経験を有し、特に海産原料を専門とする彼は、海産原料のサプライチェーンにおける責任ある調達、持続可能な生産慣行、デジタルトレーサビリティに関して、卓越した理解と知見を備えている。この専門性により、グローバル・ダイアログ・オン・シーフード・トレーサビリティ(GDST)の監督委員会や、グローバル・サステナブル・シーフード・イニシアティブ(GSSI)の運営委員会など、さまざまな理事会や委員会に参加している。また、GSA水産加工基準の策定に貢献する技術委員会にも名を連ねている。2014年以降は、マリン・トラストの改善プログラムを通じて、東南アジア、ラテンアメリカ、ヨーロッパ、アフリカ、中東地域における漁業と連携し、かつて困難を抱えていた漁業に対して前向きな法制度改革を促してきた。これらの活動はすべて、海産原料を世界にとって不可欠かつ持続可能な栄養源として将来にわたり確保していくという、彼のより広範な使命の一環である。
フランシスコは、ペルーのラ・モリーナ国立農業大学(UNALM)にて水産工学の学位を、クイーン・メアリー・ロンドン大学にて海洋生態学および環境管理の理学修士号を取得している。登壇プログラム -
平山 健史
株式会社ニッスイ
漁業養殖推進部
漁業養殖推進課
課長株式会社ニッスイ
漁業養殖推進部
漁業養殖推進課
課長平山 健史
2007年、株式会社ニッスイに入社、大分海洋研究センターにて養殖魚の防疫、健康管理を担当。2013年よりグループ会社のサルモネス・アンタルティカ社(チリ)に出向し、養殖サーモンの生産管理、技術開発を担う。2018年より現職、ニッスイグループの国内外養殖事業会社の支援、養殖フィジビリティスタディなどを担当。
登壇プログラム
モデレーター
-
前川 聡
WWFジャパン(公益財団法人世界自然保護基金ジャパン)
自然保護室
海洋水産グループ長WWFジャパン(公益財団法人世界自然保護基金ジャパン)
自然保護室
海洋水産グループ長前川 聡
渡り性水鳥の全国調査および国際保全プログラムのコーディネーター業務、WWF サンゴ礁保 護研究センター(沖縄県石垣島)での住民参加型の環境調査および普及啓発業務、海洋保護区 の設定および管理状況の評価業務等に従事後、2011 年より東日本大震災復興支援プロジェクト と水産エコラベルの普及および取得支援に加え、近年は企業の水産物の責任調達やブルーファイナンスの推進業務等に携わる。
登壇プログラム
- 資料ダウンロード
2030年目標をアジアで実現「新メタ・コアリション構想」
TSSS2024で多くの参加者から賛同いただいた2030年目標「サステナブルシーフードを主流に」を、マルチステークホルダーの協働によりアジア規模で実現する道筋を描きます。アジアのインパクトを最大化させる「メタ・コアリション構想」とは。アジア各地の主要コアリションメンバーが集結、今後の展開を語ります。
パネリスト
-
山内 愛子
株式会社シーフードレガシー
取締役副社長株式会社シーフードレガシー
取締役副社長山内 愛子
東京水産大学資源管理学科卒業。東京海洋大学大学院博士課程修了。海洋科学博士。日本の沿岸漁業における資源管理型漁業や共同経営事例などを研究した後、WWFジャパン自然保護室に入局。持続可能な漁業・水産物の推進をテーマに国内外の行政機関や研究者、企業関係者といったステークホルダーと協働のもと水産資源および海洋保全活動を展開。2019年にシーフードレガシーに入社。国内NGO等の連携である「IUU漁業対策フォーラム」のコーディネーターを務める。
-
ソンリン・ワン
青島マリーン・コンサベーション・ソサエティ
創設者兼会長青島マリーン・コンサベーション・ソサエティ
創設者兼会長ソンリン・ワン
ソンリン・ワンは、中国における持続可能な漁業、責任ある養殖、海洋生息地の再生の推進において20年以上の経験を有する海洋保全の専門家である。ザ・ネイチャー・コンサーバンシー、世界自然保護基金(WWF中国およびWWFインターナショナル)、ポールソン・インスティテュート、オーシャン・アウトカムズにおいて主要プログラムの指導的役割を担ってきた。2017年には、中国の海洋保全を推進する先進的なNGOである青島マリーン・コンサベーション・ソサエティ(QMCS)を設立し、以来同団体を率いて、多様なセクターの関係者との連携を通じて、国連の持続可能な開発目標(SDGs)と整合するかたちで中国における責任あるシーフード運動の推進に尽力している。
中国海洋大学およびイェール大学にて学位を取得。2021年ピュー海洋フェローであり、フレンズ・オブ・オーシャン・アクションのメンバー、ならびにコンザベーション・アライアンス・フォー・シーフード・ソリューションズの理事を務めている。 -
グラウディ・ペルダナハルジャ
ヌサンタラ自然保護財団(YKAN)
漁業シニアマネージャーヌサンタラ自然保護財団(YKAN)
漁業シニアマネージャーグラウディ・ペルダナハルジャ
グラウディ・ペルダナハルジャは、インドネシアおよびアジア太平洋地域において20年以上の経験を有する保全科学およびマネジメントの第一人者である。インドネシアの環境および世界的に重要な生息地の保護を支援し、気候変動への適応を促進してきた。雪をいただく高峰から熱帯の海洋環境に至るまで多様な生態系に関する専門知識を有し、海洋および陸上生態系に焦点を当てた大規模な政府助成金を効果的に管理してきた。小規模漁業管理における新たな取り組みを主導し、漁業利用権区(TURF: Territorial Use of Rights for Fisheries)の適用を含む施策を開発してきた。また、政府機関、市民社会、民間部門、地域社会を含む主要なステークホルダーとの関係構築にも優れた能力を発揮している。
モデレーター
-
花岡 和佳男
株式会社シーフードレガシー
創立者 / 代表取締役社長株式会社シーフードレガシー
創立者 / 代表取締役社長花岡 和佳男
フロリダの大学にて海洋環境学および海洋生物学を専攻。卒業後、モルディブおよびマレーシアにて海洋環境保全事業に従事。2007年より国際環境NGOの日本支部でサステナブルシーフード・プロジェクトを企画・牽引。
独立後、2015年に東京でシーフードレガシーを創立し、CEOに就任。「海の自然・社会・経済のつながりを象徴する水産物(シーフード)を豊かな状態で未来世代に継ぐ(レガシー)」ことをパーパスに、境持続性および社会的責任が追求された水産物をアジア圏における水産流通の主流にすべく、システムチェンジを牽引。
2019年には SeaWeb Seafood Champion Award リーダーシップ部門でチャンピオンを受賞。先見性のあるビジョンと、国内外の水産業界、金融機関、政府、NGO、アカデミア、メディアなど、多様なステークホルダーをつなぐ、その卓越したリーダーシップにより、アジアの水産業界における革新的なリーダーとして注目されている。
・IUUフォーラムジャパン メンバー(2017年〜現在)
・G1海洋環境研究会アドバイザリーボードメンバー(2018年〜現在)
・世界経済フォーラム フレンズ・オブ・オーシャン・アクション メンバー(2021年〜現在)
・コアリション・フォー・フィッシャリー・トランスパレンシー 理事(2022年〜現在)
・コンサベーション・アライアンス・フォー・シーフード・ソリューション 理事(2023年〜現在)
・NIKKEIブルーオーシャン・フォーラム有識者委員および水産資源分科会座長(2023年〜現在)
・水産庁 太平洋広域漁業調整委員会 委員(2018年〜現在)
・水産庁 水産流通適正化推進会議 委員(2024年)
他
- 資料ダウンロード
登壇者
-
河井 保博
日経BP
総合研究所
総合研究所長日経BP
総合研究所
総合研究所長河井 保博
ICT関連のメディアで記者活動に従事。「日経コミュニケーション」編集長を経て、2013年、クリーンテックラボ上席研究員。スマートシティ関連事業のほか、新規事業創出を目指した研究会の企画・運営、専門調査レポートの企画・執筆などに携わる。「未来コトハジメ」「DIGITALIST」など顧客企業との協業メディア企画を牽引。クリーンテックラボ所長、技術メディア(日経クロステック)ユニット長などを経て、2024年4月より現職。
登壇プログラム -
花岡 和佳男
株式会社シーフードレガシー
創立者 / 代表取締役社長株式会社シーフードレガシー
創立者 / 代表取締役社長花岡 和佳男
フロリダの大学にて海洋環境学および海洋生物学を専攻。卒業後、モルディブおよびマレーシアにて海洋環境保全事業に従事。2007年より国際環境NGOの日本支部でサステナブルシーフード・プロジェクトを企画・牽引。
独立後、2015年に東京でシーフードレガシーを創立し、CEOに就任。「海の自然・社会・経済のつながりを象徴する水産物(シーフード)を豊かな状態で未来世代に継ぐ(レガシー)」ことをパーパスに、境持続性および社会的責任が追求された水産物をアジア圏における水産流通の主流にすべく、システムチェンジを牽引。
2019年には SeaWeb Seafood Champion Award リーダーシップ部門でチャンピオンを受賞。先見性のあるビジョンと、国内外の水産業界、金融機関、政府、NGO、アカデミア、メディアなど、多様なステークホルダーをつなぐ、その卓越したリーダーシップにより、アジアの水産業界における革新的なリーダーとして注目されている。
・IUUフォーラムジャパン メンバー(2017年〜現在)
・G1海洋環境研究会アドバイザリーボードメンバー(2018年〜現在)
・世界経済フォーラム フレンズ・オブ・オーシャン・アクション メンバー(2021年〜現在)
・コアリション・フォー・フィッシャリー・トランスパレンシー 理事(2022年〜現在)
・コンサベーション・アライアンス・フォー・シーフード・ソリューション 理事(2023年〜現在)
・NIKKEIブルーオーシャン・フォーラム有識者委員および水産資源分科会座長(2023年〜現在)
・水産庁 太平洋広域漁業調整委員会 委員(2018年〜現在)
・水産庁 水産流通適正化推進会議 委員(2024年)
他
- 資料ダウンロード